第166回タスクフォース21
2025.2月例会
講演録
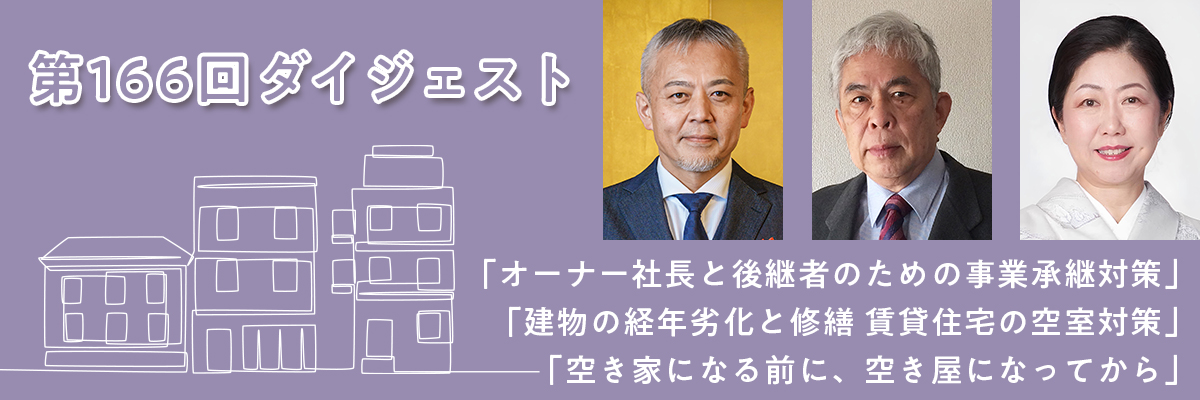
豊かで安全な日本をつなぐために経営者ができること
オーナー社長と後継者のための事業承継対策
講師:一般社団法人相続・事業承継コンサルティング協会 理事 河井 直也 氏
動画ダイジェスト版
自社株承継対策
時価と簿価の違いを活用
本自社株承継対策についてご説明させていただきます。よい会社になると利益が積み上がります。そうなると、P/L(損益計算書)でも規模が大きくなって利益が増えますし、B/S(貸借対照表)でも純資産が増えていきます。非上場株式の評価方法には類似業種比準方式と純資産価額方式がありますが、B/Sで純資産が増えていくと、純資産価額方式は当然ですが、類似業種比準方式でも株価に影響します。その会社の株式評価が高くなる。つまり、よい会社にしていくということは、株価に影響を及ぼしてしまうわけです。ですから、そこをどうコントロールしていくのかが、自社株承継対策ということになるのです。
時価と簿価の違いを活用することで、さまざまなことができます。まずは“益出し”です。たとえば簿価よりも時価が高い資産、すなわち含み益がある場合、決算書よりも実態の資産のほうが多くなっています。土地や不動産といった固定資産であれば、買ったときよりも値段が上がっているということがあるかもしれません。
会社の「見える化」と「磨き上げ」をした後、もしかしたらその不動産を売るという選択肢も出てくるかもしれません。それまでは含み益として実体化できなかったものを、売却することで実体化することができます。そして、その売却益によって負債を返済することができれば、純資産100%となるかもしれません。極端な例ですが、こういうこともあり得るということです。
さらに、これはP/Lにも影響を及ぼします。含み益を実体化したため、一時的に大きな不動産の譲渡所得益が出て、財務状況がよくなるのです。P/LもB/Lもよくなるわけですから、財務改善が行えるということになります。
一方で“損出し”は、株価の圧縮などに使ったりします。簿価よりも時価が高い資産、すなわち含み損がある場合です。これも同じように、株価を落としたいタイミングで資産を売却することで、資産の圧縮を図れます。含み損を実体化するため、資産の規模が少なくなってくるということです。それによって大きな損失が出るので、純資産や利益を少なくすることができます。
利益があれば株価が評価されますが、不動産の売却損によって大きな損失に変え、純資産や利益も少なくする。そうなると、類似業種比準方式でも、純資産価額方式でも株価を抑えることができるため、株価対策となるわけです。
またこの損出しスキームの場合、損出しして株価を圧縮したタイミングで、株式を後継者に移動します。承継のタイミングで大きな損失を出すことは、欠損金として最大10期繰り越しができますから、それ以降キャッシュフローがよくなり、多少なりともお金の回りがよくなるのです。ですから、承継タイミングでの大きな損失というのは悪いことではありません。
このように上手に活用すれば、収益改善、株価抑制の両立をすることができますので、基本の考え方として覚えていただければと思います。
不動産活用
経済面がよい会社は株式評価が高くなります。それを圧縮する方法には、主に(1)自社株評価、(2)退職金、(3)不動産活用、(4)持株会社(HD)、(5)事業承継税制、(6)生前贈与の6つがあります。
また運営面においても、株の受贈者が跡取りになるわけですから、やはり相続との兼ね合いがあります。それによって、生命保険の使い勝手も非常によくなります。生命保険は、事業承継にかかわらず非常に重要なものです。
それでは、(3)不動産活用についてご説明しましょう。………本文の続きを読む>>>
建物の経年劣化と修繕 賃貸住宅の空室対策
NPO法人日本住宅性能協会 常任理事 赤澤 泰三 氏
動画ダイジェスト版
はじめに
今日は建物の経年劣化と修繕について、また最後に賃貸アパートなどの空室対策について少し触れながら、お話させていただきます。
日本の住まいの平均寿命は30年といわれています。この数字は国土交通省の住宅局が発表しているもので、新築から解体までの平均期間になります。
海外の建物の平均寿命はアメリカで55年、イギリスでは77年となっています。これはいずれも一般の木造住宅です。これと比較すると日本は短いですが、この違いは建物に対する考え方にあります。
住宅を長持ちさせるには、計画的に維持管理することが必要で、アメリカ人は、住宅を資産として考えています。そのため資産価値を上げるために、新しく住まいを購入したその日からメンテナンスをするのです。
実際、アメリカ人は転職とともに転居も多く、生涯に平均11.7回転居するといわれます。一方、日本は平均3回。こうしたこともあって、アメリカでは転居するときに購入時より高く売るためにメンテナンスするのです。
日本でも、ようやく100年住宅といわれるようになり、政府も住宅を長持ちさせるために計画的に維持管理する必要があると訴えるようになってきました。
3つの経年劣化に向けた計画的な維持管理
物理的劣化
住宅を長持ちさせるには、メンテナンスが必要です。国土交通省が発行している「長生き住宅の手引」によると、計画的な維持管理として、「計画的な点検、補修、交換」「住宅の価値を維持・向上」の2つをあげています。
そして家の劣化は、大きく分けて(1)物理的劣化、(2)機能的劣化、(3)社会的劣化の3つがあります。
1つ目の建物の物理的劣化とは、建物の構造体や外装材、設備機器などの物理的な損傷や劣化を指します。外壁のひび割れ、塗装の劣化、外壁タイルの剥落、手すりのサビ、雨漏りの発生などが典型的な事例です。物理的劣化は、建物の安全性や機能性に影響を及ぼすため、早期発見と適切な補修が不可欠です。
外壁
一般的な外壁には、塗装外壁、ALC、外壁材(サイディング等)、窯業タイルなどがあります。意外なことですが、外壁の劣化に無頓着な方が多いのが現実です。しかし、外壁のヒビは、放置しておくと雨水が入り、吹付タイルを剥離させて、最終的には躯体に被害を及ぼしてしまいます。
ヒビにもいろいろな種類があります。………本文の続きを読む>>>
空き家になる前に、空き家になってから ~空き家活用・民泊経営について~
一般社団法人空き家空室対策推進協会 代表理事 川久保 文佳 氏
動画ダイジェスト版
はじめに
一般社団法人空き家空室対策推進協会は、空き家を活かして地域を元気にするため、増加する空き家・空室問題と、不足が懸念される宿泊施設、高齢者住宅、介護施設やワーキングスペースなどを必要とする人たち、つまり空き家・空室の貸し手と借り手を結ぶために活動をしています。株式会社エアロスペースは、こうした空き家対策としての民泊経営をサポートする会社です。
空き家については5年に一度、総務省が調査を行っており、2024年4月に公開された最新の調査結果では、全国の総戸数6,502万戸のうち900万戸、総戸数の13.8%が空き家となっていることが明らかになっています。
ただ、この数は1年以上誰も住んでいない家で、介護施設に入ってしまって実際には誰も住んでいない家や別荘などは入っていないので、そういった隠れた空き家を入れれば、実態としてはまだまだたくさんあると思います。
野村総合研究所によると、2043年には空き家率は25%にまで上昇すると予測されています。実際、戸建てに住んでいる方の実に25%が75歳以上の“お一人様世帯”ということで、今後さらに増えていくとは間違いないでしょう。
空き家が増える理由と問題点
インフラが維持できなくなる
空き家が増える理由は、少子化による家余りがあります。ほかにも子どもが地方から東京などの大都市の大学に進学し、そのまま就職して地域に戻ってこないため地方の実家が空き家になる。あるいは、戸建てではなくマンションを好む層が一定数いるということもその理由になるでしょう。
では、空き家が増えて困ることとはどんなことでしょうか。人口減少が大きな要因ですが、道路や下水道の地域のインフラ整備に予算と手がまわらなくなります。住む人が少なくなれば、鉄道などの公共交通機関の運行数が少なくなる、あるいは廃線になります。
空き家問題を語るうえで「3軒空き家になると、下水道を流れる水が減り、固まってしまう」といわれ、公共サービスのメンテナンス、インフラの維持、整備にかなりお金がかかることが指摘されています。
空き家の相続問題
空き家にしないためには、両親が健在中にその家をどうするか決めておくことが重要です。というのも、認知症になってしまうと、売ることも貸すこともできなくなってしまうからです。
成年後見人制度はありますが、………本文の続きを読む>>>